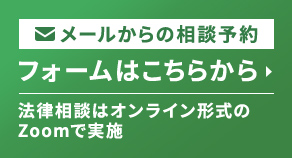入浴中の急死について
入浴中の急死で傷害保険金は
支払われるのか
皆様にとっての「お風呂での入浴」、それはおそらく一日の疲れを癒やす至福のひとときなのではないでしょうか。しかし、実際にはもっと遙かに厳しい状況が存在しています。
令和2年人口動態統計によれば、不慮の事故としての浴槽内での溺死および溺水を死因とする死亡の年間発生総数は、7,333人と非常に多い状況にあります(厚生労働省「令和2年(2020)人口動態統計(確定数)の概況」厚生労働省ホームページより。ちなみに同統計によれば、交通事故による死亡の年間発生総数は3,718人となっています)。
そして、この統計への登録は、死体検案書で死因が「溺死」と記載された例に限られるため、死因として心疾患や脳血管障害と記載された場合を含めると、家庭内での入浴中急死の実数はこの数倍にのぼる、との指摘があるのです(堀進悟「入浴関連事故の実態把握及び予防対策に関する研究」厚生労働科学研究成果データベース文献番号201315060B(2015年)、参照)。
考えたくないことではありますが、もしも皆様の家族が入浴中に急死し、しかも亡くなられた方が損保の傷害保険や生保の傷害特約・災害割増特約等の被保険者になっていたとしたら・・・・・・。
おそらく皆様の多くは、その契約をしている保険会社に連絡をすると思いますが、そのとき保険会社はどのような対応をとるとお思いでしょうか。

現在、複数の最高裁判決の影響によって、実務では、「外部からの作用による事故」であることが確認されれば、それなりの数の保険会社では支払が行われている様にも聞いています。
それは、例えば、死体検案書によって直接の死因が「溺死」であること、死因の種類が「不慮の外因死(溺水)」であることが明記されていれば、「外部からの作用による事故」であることが原則としては確認でき、しかも解剖がなされていない場合には、それを覆すような証拠を示すことは難しいと保険会社が判断しているからなのです。
もう少しわかりやすく言えば、脳血管障害などの疾病が原因となって溺死をしたとか、そもそも死体検案書自体が誤りで死因は溺死ではなく病死だったとかの主張をすることは困難だと保険会社が判断したということになるのです。
しかし、死体検案書については、保険金請求に際して用いられる場面での信頼性が完全なものとは言い難いという現状が確かにあり(そもそも死体検案書自体は保険金請求での利用を主目的として記載されるものではなく、また、厚生労働省からは同書面の記入マニュアルが公表されていますが、実際には死因や死因の種類が明確ではない場合にも医師は何らかの記載をやむを得ず行っているように感じています)、しかも亡くなられた方のそれまでの病歴が健康体での溺死と推測するにはほど遠いものであった場合などには、保険会社としても相当な調査を行い、その結果、支払を拒絶することがあるというのも現実です。
また、死体検案書による直接の死因が病死と明記されていた場合には、そもそも「外部からの作用による事故」ではないとして、支払を拒絶するものと思われます。
最近では、先に挙げた厚生労働省の委託研究が公表されたことなどにより、入浴中の急死の原因の特定は医学界ではまさに混沌とした状況になっているようにも感じています。
そして、そのような状況の中で、保険会社が行っている対応も様々になっていると言っていいでしょう(最近では、入浴中の溺死を約款上免責事由とする保険会社も現れています)。
ただ、それらの保険会社の対応に対して、場合によっては疑問となる旨を提示できるほど知識と経験のある弁護士は、ほんの一握りであると言っても過言ではありません。
訳のわからぬままに保険会社の言いなりになるのではなく、ぜひ保険法に関して専門性を持つ弁護士に相談されるのがいいのではないかと思います。
今回は、いわゆる「風呂溺」に関してお話をしましたが、病院や介護施設などでの誤嚥事故となると、被保険者が罹患していた認知症などの疾病やそこから生ずることのある嚥下障害などの誤嚥事故への影響、すでに誤嚥性肺炎を繰り返していた被保険者が当該誤嚥事故による肺炎罹患後に死亡した場合には当該誤嚥と死亡との因果関係、生命保険会社の約款で通常定められている「除外規定」の解釈、病院・医師・介護施設の誤嚥事故への対応と真実確認の困難性並びにそれに関わる賠償責任保険の取扱いなどさらに事案が複雑化します。この高齢化社会の中で保険の持つ意義は大変重要となっています。
ぜひそのことをご認識ください。